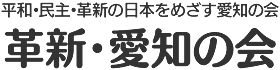受験戦争の緩和を一刻もはやく
石井 拓児 さん
いしい・たくじ
1971年生まれ。
名古屋大学大学院教育発達科 学研究科教授
専門は教育行政・教育法
教育の権利は「権利中の権利」
教育とは、人間が人間になるための大事な営みです。教育の権利は「権利の中の権利」です。教育を受ける権利がなければ、さまざまな自由や権利を享受することができないからです。教育が権利である以上、教育は無償でなければならないと考えています。お金を出さないと受けられないサービスは、権利とは言えません。
この土台としての権利がずっと侵害されてきています。そのことが、民主主義を危うくしています。日本維新の会は「無償化」を見せかけていますが、大阪の教育改革で競争を煽って「ダメな学校はどんどん潰れればいい」と言ってきた人たちです。維新の「無償化」は公立学校潰しをねらいとしていますので大問題ですし、問題外です。
競争と分断を乗り越える
日本の教育の最大の問題は、受験競争にあると思います。競争の中で多くの子どもたちと保護者が傷ついています。人間としての尊厳が傷つけられています。子どもと親が相互に傷つけてしまう場面も生まれてしまっています。
受験競争の過熱化が、教育費の問題を複雑にしています。授業料が高いことはもちろん重大な問題ですが、授業料以外の教育費として、塾や予備校、おけいこごとにもかなりのお金を使わないといけなくなってしまっているからです。中学校や高校は、教科書以外の学習参考書を大量に購入させてしまってもいます。
受験で失敗をしても、何とか教育を受けさせたいと考える人は、高い授業料を払ってでも子どもの進学を支援しようとしてきました。受験競争こそが日本の教育の問題、構造の真ん中にあると感じています。
競争して負けたやつは仕方がない、自分は競争して勝ったんだからいい暮らしができて当たり前、本人の努力の結果だという声が広く社会の中に定着してきているようにも思います。
世界ではこんな国はどこにもなく、競争の教育が基本ではありません。アメリカの場合、公立大学(カレッジ)は基本的に誰でも入れます。世界では、地域の小学校、中学校、高校に入学します。大学入試も基本的には自分の地域の大学にいきます。一部トップの大学に行く子たちもいますが、大学もバランスよく取ろうとするので学力の高い人たち、貧困世帯の学生、障害を負う学生を受け入れており、多様性を身に付けます。
日本人の場合は、競争を公平だと思ってしまっています。
こうした競争の仕組みは、お金のある人が有利なのは当たり前です。受験は同じ条件でどれだけたくさん正解を導くかですので、訓練をした人が絶対に有利です。でも、ゆっくり考えたい、自分のペースで考えたいという人は当然不利になります。サポートする大人がいれば、その力はつくようになりますけど、サポートのない家庭、サポートを受けるお金を出せない家庭は当然不利になると思います。
今の教育のシステムや制度を変えないと日本はますますダメになります。社会全体が理解しないといけない段階にあると思います。
「教育を受ける権利」の観点が弱い
教育無償化の流れは、教育を受ける権利の観点から国際人権規約に定められてもいます。
現在の教育無償化の議論は、この「教育を受ける権利」という観点が弱いと思います。どこを無償化すればいいかだけ議論していますので、維新は私学の無償化を主張し、自民党と公明党は最初これに抵抗しましたが、最後は維新の提案を丸のみしました。原理や原則がどこにもないのです。
今回の私学の無償化は、差別的な政策だと思います。公立学校は授業料以外の教育費をかなり負担していますので、私立学校の授業料だけ無償化するという流れは、明らかに平等性を失っています。こうして分断をつくり争わせておけば、政権は安泰だとでも考えているのかもしれません。
私たち専門家は「選別的無償化」と「普遍的無償化」という2つに区別しています。私学だけ無償にしようというのは完全に選別的無償化です。公立学校だけ無償化するというのも、これも選別的です。普遍的無償化という政策スローガンを掲げたい。これこそが、誰もが平等に教育を受ける権利があるという原理原則にもとづく政策スローガンなのです。
私がいちばん深刻だと思うのは、高等学校授業料を補助する修学支援制度のもと、朝鮮学校だけが支援対象から除外されていることです。真っ先に権利回復をすべき対象は朝鮮学校に通う子どもたちとその保護者です。
しかし、国会でこのことが話題にもならないのは奇妙で仕方ありません。これも特定の民族だけを排除する選別的無償制度なのです。
日本にも難民とよばれる人々がいます。日本は難民受け入れにはきわめて消極的で、ビザのない家庭の子どもたちの教育を受ける権利の保障も弱い。こうした人々を支援する市民団体が立ち上がっています。名古屋大学の学生が、そうした団体と街で出会って加わっています。感動します。
無償化への逆向きの声は
「大学無償化はクズ大学を生き残らせるだけ」「高校無償化は大阪維新が喜ぶだけ」というようなものがネットで大量に流れています。無償化に対する乱暴な意見が出てくるのは、権利という観点が弱いからです。 高校や大学の教育を受けることは、今や、とても大事な権利の一つになってきたと言うべきです。新しいリテラシーが求められている新しい時代に入ったことは間違いありません。
このことを理解せずに、お金がない人は高校や大学には行かなくてもよいとか、アルバイト漬けで勉強する時間を確保できない学生を放置してもよいと考えるとすれば、今後、間違いなく日本は世界から大きく後れを取ることになります。
教育無償化の理念をもとにした政権を
一人ひとり特性が違い、一人ひとり発達の目標が違います。文字が読めないだけで、能力がないと誰が判断できるでしょうか。そうした子どもや青年たちのなかにも、高い能力を持っている人がたくさんいるのです。
ほんの少しの支援さえあれば、能力を生かして立派に社会に出られる人がたくさんいます。大学の無償化は、高校までの教育ではまだ十分に開花できなかった能力を、もういちど引き出す機会を提供することにつながります。大学を既に卒業した人たちや、60代以降のすでに退職をした人々、まだ大学で学んだことない人たちを含め、もう一度、大学に入って勉強してみたいというすべての人々の権利保障につながっているのです。
受験競争を一刻も早く緩和すること、教育を受ける権利をあらためて確認し、すべての学校段階の教育を無償で提供することが求められています。その方法はたったひとつしかありませんし、それは難しいことでも何でもありません。それは、この理念をもとにした新しい政権枠組みをつくることです。日本社会の将来をまじめに考える人であれば、だれでも賛同できる政権公約となるはずです。
革新懇には、こうした政策を大きく打ち出して、大きな世論の広がりをつくってほしいと期待しています。