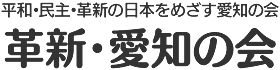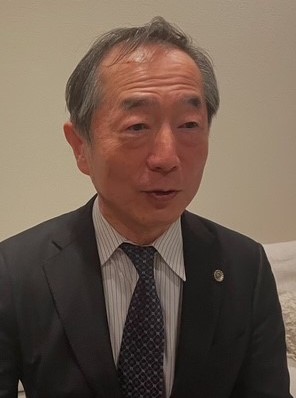
夫婦同姓制度は憲法に反する
伊藤 倫文 さん
いとう・みちふみ
1961年生まれ。
愛知県弁護士会会長(2024年4月1日就任)。日本弁護士連合会副会長(2024年4月1日就任)。
「選択的夫婦別姓」導入へ
愛知県弁護士会は2024年7月23日に「選択的夫婦別姓の導入を求める会長声明」を出しました。
この問題は、すでに、1996年に法制審議会で選択的夫婦別姓を導入する内容の答申が出されていますが、愛知県弁護士会では、1990年に選択的夫婦別氏制を採用すべきとの意見書を出しており、その後も、2010年3月、2018年8月にも会長声明を発しています。そして、2021年6月23日、最高裁判所大法廷決定(以下、最高裁決定といいます)において、夫婦同姓を強制することを合憲と判断したのを受けて、同年7月にも、選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明を出しています。
このように、愛知県弁護士会では、意見書のほか、何度も会長声明を発出してきましたが、2024年6月に、日本弁護士連合会の定期総会において、選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議を行い、また、経団連においても、同月に選択的夫婦別姓を求める提言を行いましたので、改めて、2024年7月に会長声明を発出することにしました。
「夫婦同姓制度」は憲法違反
民法750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めて、いずれかの姓を名乗る形で夫婦同姓を義務づけていますが、現実には、約95パーセントは女性が改姓しています。
2021年の最高裁決定は、民法750条の規定は憲法24条に反するものではないとしていますが、4名の裁判官は憲法24条に違反するとの判断をしています。しかも、多数意見においても合憲との判断をしていますが、夫婦の氏についてどのような制度を採るのかは立法政策の問題であり「国会で論じられ、判断されるべき事柄」であるとしています。
「氏名」は個人の人格の象徴であって、アイデンティティに関わる非常に重要なものです。本来、結婚は、両性の合意のみに基づいて成立すべきところ、氏を変えないと結婚できないのは憲法24条1項に違反し、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すると定める憲法24条2項にも違反します。 そして、法の平等を謳う憲法14条にも関わる問題でもあり、「夫婦同姓制度は憲法に違反する」ものといえます。
このなかでも、私は、一番はアイデンティティの問題であると思っています。その人がその名前で生きて、それを強制的に変えないといけないのは「すべて国民は、個人として尊重される」ことを規定する憲法13条に違反するものと考えます。
なぜ、日本だけが「夫婦同姓」か
夫婦同姓を義務としている国は、世界の中で日本だけで「選択的夫婦別姓」の導入について国連から4度目の勧告を受けています。
なぜ、日本だけが「夫婦同姓」なのかといえば、最終的には政治の問題ではないでしょうか。
家制度、戸籍制度が崩壊するのではないか、あるいは宗教にも関わるものかもしれませんが、一定の保守派の方々の根強い反対があるために、なかなか法案として出せてなかったのが現実だと思います。
選択的夫婦別姓導入の反対論に対して
反対論にはいろいろありますが、特徴的には4つぐらいにまとめられると思います。
一つ目は、「家族の一体性を崩す」という反対論です。
実際には、事実婚でやってみえる家族や、外国籍の方も、家族の絆を持っておられるわけで、それを外から「一体がない」という話ではないと思います。それぞれの意見や価値観で、同姓・別姓を考えればよいと思っています。
二つ目は、「子どもの姓をどうするか、兄弟で姓が違っていいのか」という反対論です。
子供の姓については、選択的夫婦別姓の導入を考える立場でもまとまっているわけではなく、法制審議会では、結婚時にどちらの姓を名乗るかを決めるとの考え方でした。また、子どもが生まれたときに子どもの姓を決めればよく、決まらない場合には、家庭裁判所で決めるとの考えもあるようです。ただ、家庭裁判所で決める基準も難しいと思いますので、私は、婚姻時でも出生時でも夫婦でどの姓にするかを決めることは認めつつ、特段の意思がない時には戸籍の筆頭者の氏にするなどを規定しておくのがよいのではないかと思っています。そして、子どもは、一定年齢になったときに、家庭裁判所の許可を得て、同じ戸籍内で氏の変更ができると考えられています。
なお、「子どもの姓を親が強制するのはどうか」との意見もありますが、名前だって親が決めているわけですから、あまり理由にはならないと思います。
三つ目は「通称使用の拡大で足りるのではないか」という反対論です。
実際に通称も広がっており、旧姓が多くのところで認められています。マイナンバーとか免許証だとかパスコードなどいろいろなところで通称は認めてはいるけれども、併記しているんです。
経団連は、婚姻時に氏が変更することにより、女性が社会進出するにあたっての妨げになりかねないことを強調しているようにも思います。
もちろん、氏を変更することでの不利益はあるでしょうが、その不利益を完全になくすことは難しいでしょうし、そもそも、本質的にはアイデンティティの問題だと思っていますので、通称使用拡大では解決にはならないと思います。
結局、選択的夫婦別姓を法制化したくない人たちがいろいろ理由をいっていますが、重要なのは、自分の姓を変えることに抵抗感を持っている方がいる、それは尊重しなければならない、選択できるというただそれだけです。
なお、四つ目には、「賛否の意見があるので慎重な検討が必要で、拙速の結論は不可」という反対論もあります。
ただ、法制審議会の答申がでてからも30年近く経っています。
2021年の最高裁決定は「(制度の在り方は、)国会で論じられ、判断されるべき」と指摘をしており、それ以前の2015年の最高裁大法廷判決も同様の意見を示しているにもかかわらず、立法不作為の状態が続いています。
政治が国民の意思を汲み、決めるべきと言われていながら、ずっと何十年も経ってやられていないことが問題です。
それぞれの地方や議会へ地域から声をあげて
選択的夫婦別姓制度は、今の戸籍制度は残した中で、結婚したときに氏を変えるかどうかだけの問題です。
いま国会の中で論議がされていますが、大多数の国会議員は導入に賛成と思われます。それぞれの地方での議会、より住民に近い立場の意見を反映する場でも「選択的夫婦別姓」への声をひろげていくことが大事だと思います。